海外就職の際に必ずと言って良いほどお世話になるのが人材エージェント。
求人の紹介から、面接の設定、入社後のフォローまで、最初から最後まで関わることになる。
特に海外の場合は、自社採用を大々的にやっている場合は少ないので、人材エージェントを通じて就職活動を行うことになる。
そんな人材エージェントではあるが、気をつけないといけないことがある。
それは、人材エージェントの言うことを鵜呑みにしてはいけないと言うこと。
東南アジアで人材エージェントとして勤務した経験から、その理由について解説していく。
こんな人向け
- 海外転職活動中
- 既に、海外で働いている
- 現地採用、海外就職に興味がある
人材エージェントの収益構造

まず、エージェントがどのように収益を得ているのかを説明する。
端的に言えば、紹介した求職者を採用した企業から支払われる手数料で稼いでいる。
求人をもらった時、求職者と面接をした時には手数料を支払われることはない。
あくまでも採用まで至ってから支払いが発生する。
なので、全く同じことだが採用に至らなければ支払いは発生しない。
このビジネスモデルにおいて、求職者がお金を払うことはまずない。エージェントへの登録、履歴書の添削、転職全般のアドバイス、さまざまなサービスを無料で利用できる。
採用というゴールのために、多くの求職者を集めて企業に斡旋をしまくる。
求人を得るための営業活動、求職者へのさまざまなサービス、全ては採用というゴールのために存在する。
そこから考えると、人材エージェントにとってのお客さまは求職者ではなく、企業ということがわかるだろう。
これらを前提として考えると、本記事のタイトルの意味がわかるだろう。
以下、注意点を記載する。
情報発信に注意

単純化すると、人材エージェントは、できるだけ多くの候補者を集める必要がある。そのためには、頻繁にセミナーを開いたり、海外生活=楽しいものというイメージを作る必要がある、
騙してやろうと言う意図はないが、楽しそうと思ってほしい、と考えながら情報発信をするので必然的にそうなってしまう。
また、一見華やかに見えるので、一時期は各種メディアで現地採用がもてはやされていた時代もあった。
現在は、ネットの普及によって情報が手に入りやすくなったため、メディアは完全に嘘の情報は流しにくい。
ただ、さまざまなブログや、人材エージェントの発信を見ていると、マイナス面を伝えていない、過小に伝えている場面が多く見受けられる。
休みの日の旅行、アフターファイブでレストラン、ランチの豪華なメニュー、スパ、仕事面でのやりがい、成長、、、
気になる人はブログ、Youtube、インスタ、を見ていただければと思う。
日々のストレス、長時間労働、悩み、アフターファイブどころじゃない、
なんて話は滅多に見ない。
情報発信の目的や、人材エージェントが工数を投入してマイナス情報を流す義務はないので、そこに対して非難はしないし自分でも同じことをすると思う。
マイナス面ばかりに注目する必要はないが、人材エージェントをはじめ、情報発信者が何を目的に情報発信をしているのかを気にした方がよい。
転職活動の際の注意点

情報発信以外に転職活動時に気をつける点を記載する。
人材エージェントはビジネスを行なっていて、決してボランティア団体ではない。
営業会社なので、担当者は日々の成績に追われることになる。
何件の求人を獲得した、面接を何件組んだ、何件オファーまで至ったか。
こう言った数字を毎日進捗管理され、上司に檄詰めされている。
なので、各担当者はこの数字を必死に達成しようとする。
そうすると、求職者が急いでいなかったり、希望と異なる求人だったとしても、
”試しに受けてはどうか”、”採用は縁、希望に合った求人は難しい”、”良いタイミングを待っていても来ない”
こう言ったことを言われて、なんとなく言われるままに面接を受けたり、入社してしまったりする。
海外就職という華やかな生活に惑わされて正しい判断ができなくなる。
エージェント側は、一見求職者のことを考えているようなことを言う。確かに、明らかに希望にあった求人はない状態で、希望に近しい求人が出てきた時、明らかに好条件の企業からのオファー、など、求職者の後押しをした方が良い場面も多くある。
ただ、背景にあるのは(気にかけている)のは自身の成績というのも真実。
家の営業と同じだと思えば良い。
”こんな条件の戸建なかなか出ませんよ”、”希望には会っていませんが、そもそも全ての希望にあったものはなかなかない”、”縁です。”
そこに嘘はなくても、純粋100%に相手のことを考えているわけではない。
最後に
希望を抱いて行動を起こす、とりあえず飛び込んでみる、全く反対はしない。
ただ、冷静に情報を見定めてほしい。
くれぐれも、騙されたという結果にはなってほしくない。
人材エージェントも騙そうと思っているわけではないし、候補者も不幸になりたいわけではない。

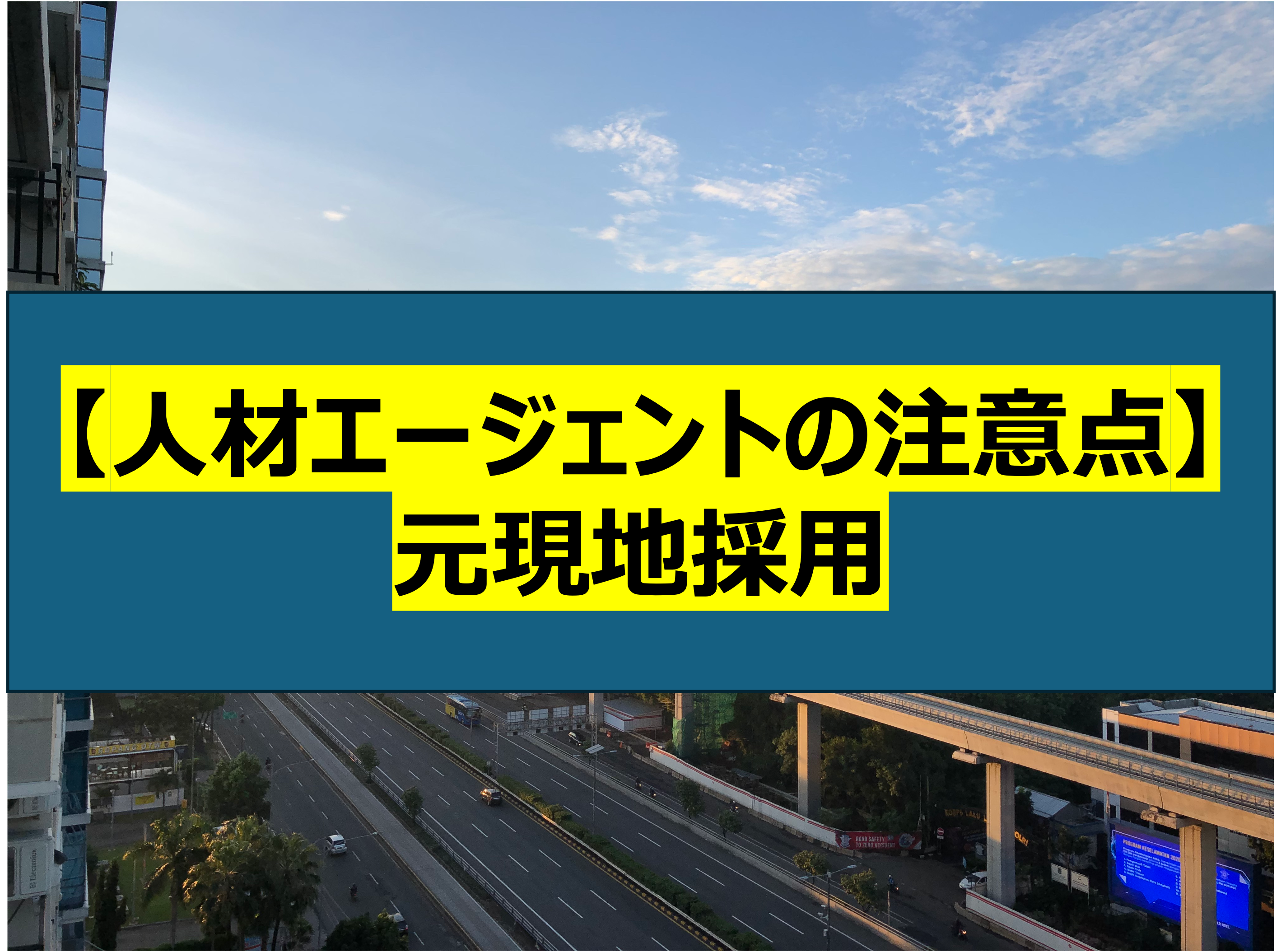


コメント